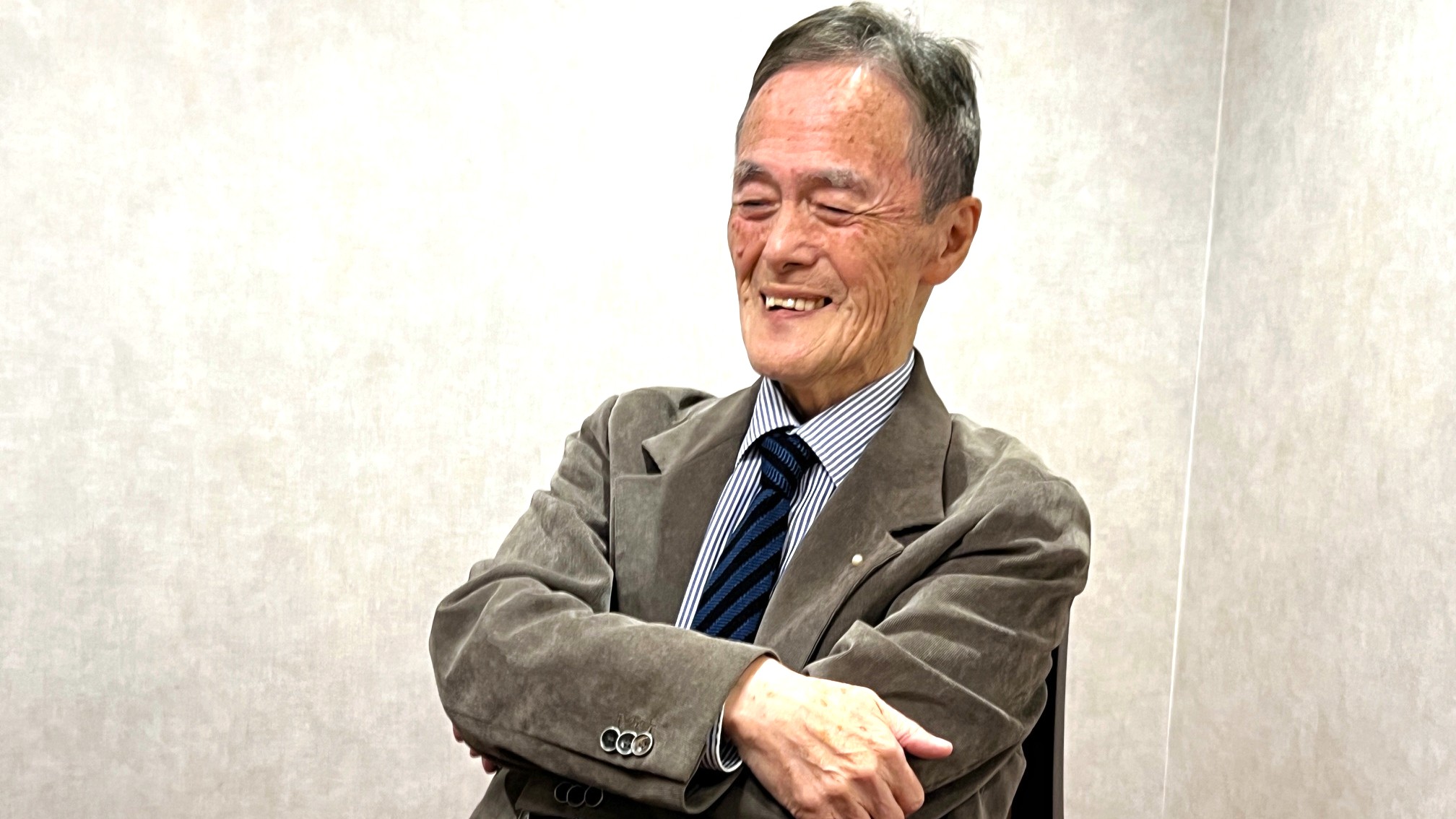高津隆氏は1965年(昭和40年)に西武百貨店に入社し、池袋店食品の干物(塩干物)売場からキャリアをスタートした。当時はまだ堤清二氏は池袋店長にもなっていなかった。塩干物の後に塩鮭売場なども経験し1年ほど経った時点で、当時の山崎食品部長(後の社長)から秘書室に誘われたが、自分に合わないと考えて断った。次に池袋食品部は自営精肉売場を始める事になり、山崎部長からはスライサーを導入するから2週間で精肉業をマスターするよう、無理を承知での指示があり、スーパーの精肉売り場で一通りの研修で精肉業の概要だけは理解できた。しかし実際売場を始めてみると、精肉業は危険を伴う肉体作業の割に、なかなか利益も出せず苦しみ、売場にロースターを入れてもらってローストチキンを作る事でなんとか利益確保するなど悪戦苦闘の毎日だった。7年ほど経ってから商品部に異動した。当時の西武の食品売場は競合他社や駅ビルが業者任せが多かった中、自営で何事にも挑戦し汗をかく仕事であったため、帰宅の電車の中で袖口に鮭の鱗がついていたりした。苦しかったが、現場の仕事は同期の中でも自分は仕事をやっているという充実感があった。
44年前の10月8日に西武池袋に「食品館」がオープンした。食品は地下2階にも増床され、ここに一流レストランのイートインとテイクアウトの両方ができる「ホットデリカ」や、地下1階に新たにできた南コンコース入口にはパリの「ルノートルのブーランジェリー(パン売場)」が登場、その後ろには「京都錦小路」などなど、全て現地にいかないと出会えない本物ばかりで従来のデパ地下の常識を超える食品売場が誕生した。当時の西武はパリ駐在部に邦子役員がおられ、フランス情報にも恵まれていた。そこで海外催事のフランス展を契機に食品部もフランス出張するようになり、食品の高津氏など各領域4人ほどのメンバーが3週間をかけて現地出張した。高津氏は1970年代以降のヌーベルキュイジーヌの三ツ星シェフ、ブルゴーニュのポール・ボキューズとカンヌ近郊、ムージャンのムーラン・ド・ムージャンのオーナーシェフ、ロジェ・ベルジェと交渉を重ねた。当時はこの二人とルノートルの三人が世界から最も注目されるシェフであった。堤清二氏は何でも自分でやってみて出来上がったものしか認めない。「自分でやらないとその本質は分らない」といつも言っていた。この点は競合他社の百貨店経営者と全く違っていた。しかしこれは社員にとっては厳しいことでもあったので、厳しい仕事に耐えられずに中途退社する社員も多かった。堤氏は経営幹部には厳しかったが現場社員にはいつも優しく、興味を持って話を聞いてくれた。食品売場は売上規模も大きく、売上は毎年伸長していた。当時の百貨店はまだまだ衣料品中心だったが、衣料品は同質化と価格競争も始まっていた。その点で百貨店の食品領域は独自性で勝負できた。それまで百貨店の顔ではなかったはずの食品のポジションはこのころから次第に高まり始めていた。
当時の関東は豚肉文化圏で売上の多くが豚肉だったが、このころから関西の牛肉文化が関東でも定着し始めていた。そこで恐らく多くの人が日本一と認める精肉店であり明治村の中でも、明治時代の本店が今も当時のままの姿で営業・保存されている神戸の「肉の大井」を導入したいと考え、先々代主人に出店要請するため、神戸まで新幹線の日帰りを7回繰り返した。神戸では、池袋の西武百貨店は当然無名の百貨店でしかなかったので、最初は店頭で話を聞いてくれただけだったが、説得を続けた結果、しだいに関心を持ってもらえるようになり、7回目にしてようやく4階のレストランでステーキをごちそうになり、交渉が前に進んだ。
しだいに「肉の大井」は東京でも大きなビジネスになっていったが、先々代社長が亡くなったことで、関東の店を全て撤退ということになってしまった。しかしお客さまの高いご支持を集めていた「肉の大井」をそのまま無くしてしまい、多くのお客さまを失望させたくなかったので、大井の先代社長に交渉し、大井の番頭格だった森安氏に東京に残っていただくよう要請した結果、「肉のもりやす」が誕生し、毎日行列ができる人気店となったが、この出店は関東の精肉業界には大きな刺激となった。本当に良い物をきちんとお客さまに届けたいという理念だけでどんどん進めた結果、これが実現できた。
誰でもが知る横浜中華街の名店との交渉も多くのスタッフがストーリーを作り、体を張って汗を流して毎日交渉に行ったことで道は開けたが予期せぬトラブルにも見舞われ苦労の連続だった。大宮店の故内山店長なども最も若手として、この交渉に当たっていた。食品館の経験は貴重なものであった。こうして導入した名店のすべてが必ずしもバランスシートが良いというわけではなかったが、西武側はそれに耐えた。これらの名店の存在感は西武の食品売場の顔になり、売上や効率だけでない価値がうまれてきた。
競合百貨店の食品領域の先輩方が池袋に来店され、「どうしたらこんなことができるのか?」とよく聞かれた。もちろん古い業界組織の秩序にがんじがらめになっていてはできない。しかし自分は社内外の人たちに恵まれていたのだと思う。自分の入社した1965年は、思い出したくないほどの大不況で、入社試験も大変だったが、それだけに西武にも骨のある人材が入ってきたのだろう。当時の堤清二氏は池袋店長にもなっていなかったが、下っ端の自分たちが頑張ってやった仕事を報告する話を聞くのが好きだった。しかしいつも最後に必ず次の段階へのステップアップの宿題を出す事も忘れなかった。
西武の関西店舗は高槻、大津、八尾、つかしんなど、どれも郊外店舗であり、大阪中心部では一流とみなされていなかった。そごうと経営統合されて初めて心斎橋という大阪の中心部に出て、「そごう」が持つ伝統に培われた関西でのお客さまの期待と信頼感の西武との違いを強く感じた。
自分は当時の食通が通っていた麹町の「うなぎ秋本」の先代秋本社長から、関西と全く異なる江戸前鰻料理への深いこだわりと多くの知識を教えられた。先のポール・ボキューズやロジェ・ベルジェが来日したときも「うなぎ秋本」に連れて行ったが、二人とも本物の味を大絶賛していた。どんな有名店でもブランド名に寄りかかって、クオリティを忘れるとお客さまに対する詐欺行為になる。それをちゃんと判定するのも百貨店人の責任だと思う。こういう筋の通しかたは今の西武そごうの食品部にも継続していってもらいたいし、そのためには汗を流さないとならない。人任せのテナント型ではできないと思う。食品や菓子など、どんな領域や業種にも日本一と評される店があるものだ。口うるさい創業者やオーナー経営者が頑固に品質を守る名店には動かしがたい哲学があり、それが商品やサービスにまで、ちゃんと反映されている。小売の人間は、それを売場でお客さまに体験していただき、伝えられないといけない。百貨店で大量販売したら品質低下するのではないかと心配するオーナーと交渉してやっと出店にこぎつけた1855年創業の加島屋や、歴史的に守ってきた品格や哲学を表せる売場作りにこだわってきた虎屋や、年末に商品を切らさないよう細心の努力を払ってきてくれた長崎の福砂屋などの名店を、同業他社と横並びにするわけにいかないことを自分は嫌というほど学んできた。名店商品を扱うには、相手の哲学を深く理解しないといけない。これは食品領域だけに限らないと思う。
百貨店の売場には良い取引先がいてくれて、そこで充分に力を発揮できていることが大切である。だから常に顧客目線で売場の状態に目を配るプライドある社員がいつも売場にいることが必要だろう。今の時代には今の時代の論理があるだろうから、自分たちの世代のやり方が全面的に正しいとは言わないが、今はこれからの時代の「テナントビルではない百貨店のありよう」が問われていると思う。もっと明るくエネルギッシュに働いてほしい。昔、多くの名店と苦労して交渉を重ね、出店してもらったときは他とは違うそれなりの環境を作り、お客さまには雰囲気からその価値を分かってもらえるようにした。そうでないと彼らの力も発揮できない。「京都錦小路」や「横浜中華街」も他と同じ横並びのフラットな演出ではなく、特別な演出で売場に新しい刺激を生んだ。名店の鰻も寿司も思わずその店のものを食べてみたくなる演出があった。来店していただいたお客さまに感動してもらい、良いものを発見してもらい、それらと出会って楽しい暮らしをしていただくのが百貨店のミッションであり、そのために働くのが百貨店人だろう。堤さんは食品に詳しいわけではなかったが、食品は口で食べるだけでなく頭でも食べるものだ。だから食品メンバーは堤さんがまだ知らない素晴らしいものを店に出してやろうといつも挑戦してきたが、堤清二氏はそこで立ち止まることは許してくれなかった。一つ実現すると褒めてくれたが、またバーを上げ次の宿題を出した。その進化へのこだわりの緊張感をいつも作りだしてきた堤清二氏の下でなければ、池袋の食品館はできなかっただろうし、今の食品売場の隆盛もあり得なかったと思う。歴史のない会社でありながら、半面古い仕事の仕方へのこだわりもなかった。そういう中で今まで挑戦と失敗の連続にも関わらず、何とか走り続けてこられたのは周囲の人たちに恵まれていたからだと思う。