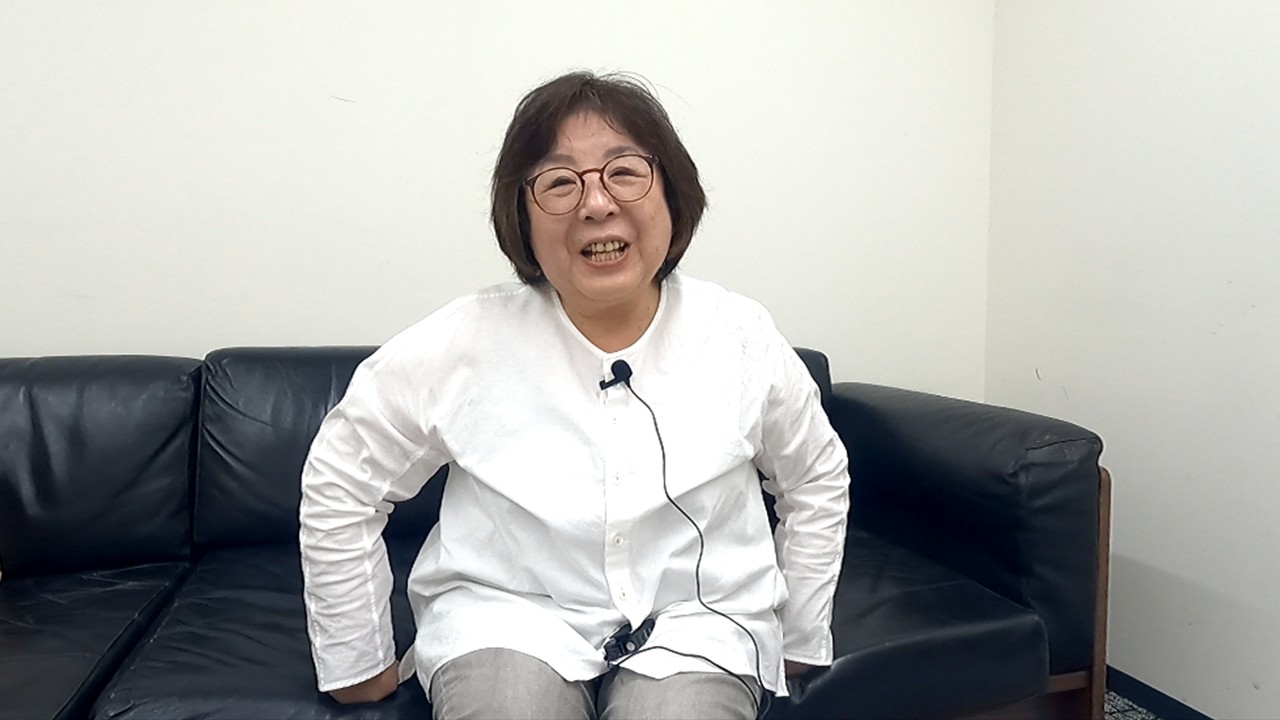岡しげみ氏は、美大大学院修了後海外で美術の保存修復の教育を受け、84年に西武百貨店に入社し文化事業部西武美術館に配属。西武美術館が誕生する前の70年代の美術展は公立美術館や百貨店催事で行われる、型にはまった泰西名画、工芸や美術史をなぞるものが多かった。しかし、西武美術館は、マン・レイ、マルセル・デュシャン、クリスト、ジャスパー・ジョーンズ、荒川修作といった作家による現代美術家や、ロシア・アヴァンギャルドなどそれまで公立美術館が積極的に扱ってこなかった領域を紹介。さらに、安倍公房の演劇、三宅一生のファッション展、多くの女性に衝撃を与えたレ二・リーフェンシュタールの写真展など、今では珍しくなくなった美術・工芸だけではない表現を紹介するなど、時代を先取りした挑戦的な美術館だった。自分は84年、入社早々、百貨店のエジプト催事に関連した「黄金のファラオ展」担当した。文化事業部/西武美術館は、池袋以外に船橋西武美術館、池袋アート・フォーラム、有楽町アート・フォーラム、シード・ホール、関西のつかしん、八尾、大津、札幌五番舘、各地の西武系列の百貨店の催事場やホールで展覧会を開催。軽井沢高輪美術館では、若手美術家が指導する子供向け夏休みアートワークショップも行った。百貨店12階の西武美術館時代は「堂本尚郎」を担当し、「ポストもの派の展開」などに携わった。89年に1階に降りてセゾン美術館となりその柿落しの「ウィーン世紀末」は、クリムト、シーレ、ココシュカをはじめ多くの工芸、デザインで構成され、メンバー総動員でプレビュー当日の朝まで展示作業が続けられた。この展覧会は大盛況で、クリムトの《接吻》を用いた展覧会ポスターは掲示場所から盗まれたこともあり、増刷され、図録も完売。その後は、「ワイエス展(ヘルガ)」、「ソナベント・コレクション」、3回シリーズの「日本の眼と空間」などの企画に参加。担当したポーランドの女性立体作家アヴァカノヴィッチの展覧会では、展示台の高さを背の高い作家本人の視線ではなく、日本人の視線に合わせ岡さんの見やすい高さにするように言われ、見る人がいて作品になるということを教わった。ポーランドの芸術家・演出家のタデウシュ・カントルの展覧会では《死の教室》の舞台装置である幾体もの人形が座る教室の展示が不気味で、時間外にそのそばを通ると人形の数が変わっているように錯覚したこともあった。アメリカの作家リチャード・タトルは、作家が好きな作家と言われており、当時サンタフェのネイティブアメリカンがかつて暮らしていたメサ(テーブル状の丘/台地)にアトリエを構えており、現在も小山登美夫ギャラリーで展覧会が開かれている。また、セゾン美術館以降のアートディレクター 松永真の個展も手掛けた。サブ担当として「紫禁城の后妃と宮廷芸術」、「イサム・ノグチと北大路魯山人」や「柳宗理のデザイン」に携わった。柳宗理は、64年の東京オリンピックの聖火トーチや高速道路の遮音壁、今も続くベストセラーの鍋などの料理器具やカトラリーをデザインしたことで知られている。また、担当外の展覧会、特に海外から来た作品の点検や状態調査を行った。堤清二氏は、展覧会を観終わったあと、気に入った展覧会の図録は自分自身で買い求め、その展覧会の担当者が誰かを尋ねたそうだ。セゾン美術館のただの白い箱ではない展示環境は、展示構成の工夫の余地が多く、作家にとってもインスタレーションの創造を掻き立てられたようであった。セゾン美術館では枷がないことから、学芸員は自由に展覧会を構築することができた。さらに、池袋以外の多くの拠点でも展覧会作りを経験したことで、学芸員は鍛えられていったと思う。
F8
元西武美術館、セゾン美術館学芸員
岡しげみ
(撮影日:2025/08/14)