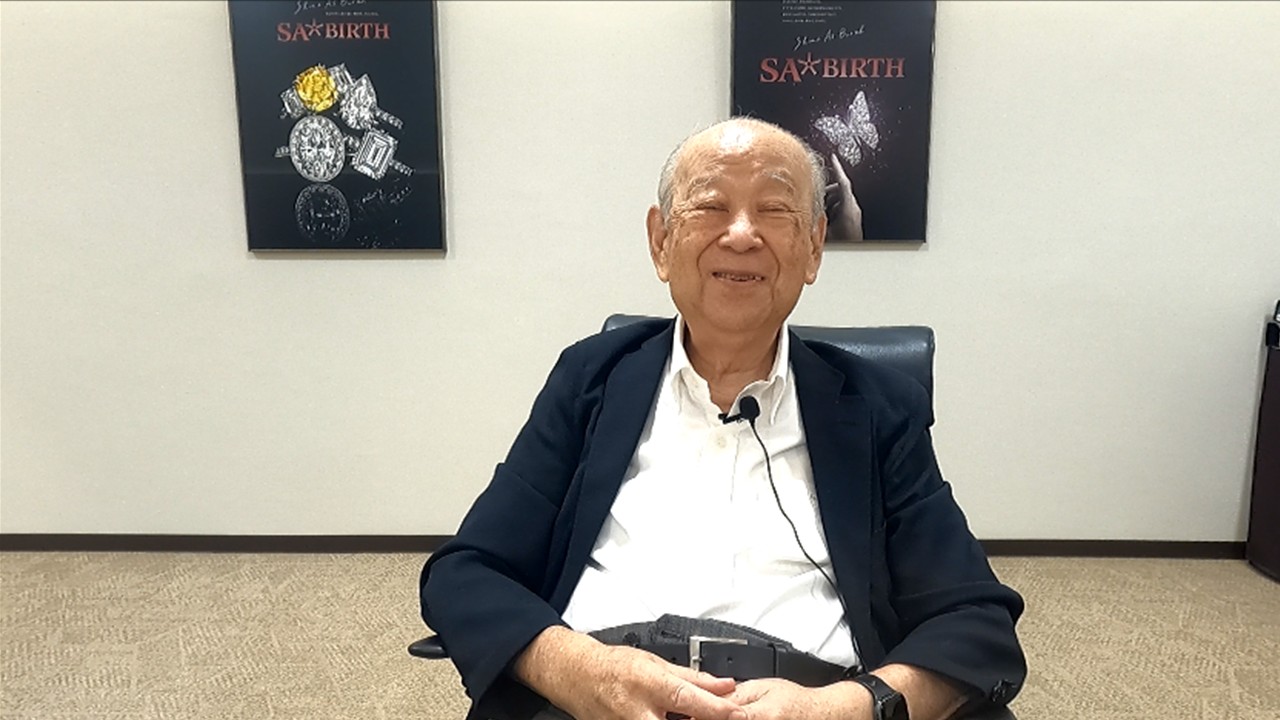米谷浩氏は昭和33年1958年大卒3期生として西武百貨店入社。同期は10人ほどで早大卒が多かった。紳士服に配属され、後39歳で取締役商品部長。米国シアーズに2週間の研修に行った後に池袋9期増床の構造改善となり、従来の商品別・アイテム別の商品提供から「ライフスタイル別にまとめた商品・サービスの提供」を日本の百貨店で初めて転換し、豊かな生活の芽生えに合わせて、ニーズ商品のみではなくウォンツ商品の充実を図った新しい百貨店を誕生させた。今井氏と交代で池袋店長になったが10期増床では、池袋の街機能への提案を含め、美術館、スポーツ館、コミカレなど、モノだけではなく、新しい生活の情報発信基地として規模を日本一にひろげ、売上日本一を達成した。3年半の後、当時買収した西武クレジットの旧緑屋(現クレディセゾン)に異動となる。当時からサンシャインビルの52階に本部を置いていた当時の西武クレジットは当初小型店での割賦販売業であった。全店を視察したら、多くが駅裏の目立たない立地で建屋の上にボウリング場跡地があったり、風俗街立地さえあり、あまり胸を張れる雰囲気ではなかった。緑屋も丸井も戦前は同じ割賦販売業者にいて戦後郷里から戻り、それぞれに分かれて割賦販売業を始められたということだった。 緑屋に行ってみて初めてベッドや家具家電の売上は西武より大きく、バイヤーの取引先での信用度も高い事が分かった。緑屋にはこれら領域の優秀なバイヤーがいることを活かして、衣料はやめて専門大店化して、将来どこかカテゴリーキラーと一体にすることで、百貨店からなくなるアイテムを止めることもができないかと考え、渋谷道玄坂店を当時まだモバイル商品もない時代にオーディオに焦点をあてた展開を試みたがうまくいかなかった。これは本来は新たなカテゴリーキラーに成長させることもできたはずだった。しかしここは自分の知っている小売業とは違うものだと思った。また割賦販売のため、月々の支払額をきりの良い数字にするため、プラス1品をお勧めする販売が定石であり、販売点数を上げるノウハウもあった。たまたま八戸の店を視察に行ったとき、盛岡に戻る列車を待つ間、近くの本屋で日刊工業新聞が出版していた「銀行の消え去る日」という本に目が留まり、キャッシュレス時代のことが書かれていて、これからは銀行よりキャッシングの時代だというフレーズが気になり、緑屋の与信能力を使えると思いつき、この方向の成長の可能性を考え始め、ビジネスモデルを変える事で生き残れると思った。当時全国の緑屋の不採算小型店を閉鎖し始め、エリアによっては社員を競合店に紹介するなど大変であったが、一部しっかりした店舗は存続させることにした。これは当時通産省管轄だった総合割賦店は大蔵省管轄の金融業より税制面で利点があったから小売業の看板を下ろさないほうが良いと判断したからである。堤会長に対しこの会社をカード会社にすべきだと提言し、まずATMでのキャッシングを始めてみた。当時坂倉氏が西武クレジットの社長であったが、竹内氏が次の社長に決まっていた。しかし、現場で細かく指導する役割の人物が必要だと考え、宇都宮に配属されたばかりだった林野氏を、坂倉氏に頼んで西武クレジットに呼んでもらった。一方で坂倉社長は古巣の三越から帰ってきてほしいという要請がきていた。
自分が入社したころの西武百貨店は6回目の増床をし巨大化し始めたころだったが、九州出身で三田に通っていたので中央線以北の事情を殆ど知らなかった。だが売場づくりには学生時代の新聞活動が役に立った。当時大学新聞と三田新聞しかなかった慶應義塾に3つ目の新聞として入学シーズンと早慶戦の時だけ発行するジャーナリズム研究会があったが廃部の危機にあり、頼まれて友人たちと新聞作りを見様見真似で始めた。メインの記事や目を引くトピックス記事など、新聞作りのノウハウがそのまま売場づくりに繋がっていった。早慶戦の神宮球場では売上を上げるための販売方法も考えた。またOBとの対談記事なども新入生に好評で、いつしか15人のジャーナリズム研究会に入部希望者が100人も押しかけるようになり、今やこのクラブのOBに新聞記者や政治家も輩出されるようになった。
自分の実家は小倉の小さな地方百貨店をやっていたが、小倉の大火で全焼して廃業となり、アルバイトで生計を立てることになった。慶應義塾では7割が自宅通学者で自分は少数派だった。銀座のドイツ料理ケテルのビルの上にラジオ番組のダビング録音スタジオがあり、ここで地方ラジオ局用に東京キー局の番組をテープ録音し複製し配給する仕事のアルバイトを週3回深夜までしていた。このアルバイトは月収12000円になり、西武の新入社員給料が9500円だった時代を考えると高給だったが、下宿代を払うと食べるのがやっとで洋服代もままならなかった。
西武クレジットから百貨店に戻ると、社長は山崎氏で和田氏は西洋フード社長になっていて、米谷氏は全店の店舗運営部で全店の統括をしていたが、塚口のグンゼ工場跡地に本格的ショッピングセンターを作る計画で西武百貨店関西の社長として大阪に単身赴任した。関西には関東とは異なる地域事情があり、既存の関西系百貨店が出店しない地域に後発の西武が出店したため、出店当初は物珍しさもあって、それなりの実績をあげたものの、開発時の無理な条件で経費がかさみ成功せず、「つかしん」の生活遊園地というコンセプトは西武らしくもあり、話題となったが、東京郊外の二子玉川のような立地とは異なり、大阪、神戸からの集客は困難で、当初の扱い商品も地元消費者のニーズとは合わず、コンセプトを反映した施設づくりや街づくりのコストもかかり事業部門として会社に貢献できなかった。この時は、小倉高校の後輩が毎日新聞の編集局長で大阪にいて、いろいろと加勢してくれたおかげで多くの面で助けられた。しかい、最終的にこれらの計画は国土計画と対抗するような不動産事業であり、セゾングループの体質が元で失敗したのが残念であった。
このころは、地方の提携店から西武百貨店になった店からおきたおかしな勢力を排除する必要があったが、これにより関西担当を外されたため、辞表を提出したが、堤会長と相談するように言われ銀座のホテルで面談し、これらの問題点を会長に説明したところ、一旦和田氏のところへ行くよう指示された。このころ和田氏は全国に展開するファミレスのシステム化を行い基準化・標準化を進めていたが、百貨店にその発想はなかったので、ここでその手法を学び、のちに百貨店でも基準化・標準化を始めるノウハウができた。
西洋フードでは九州のフードチェーンを買収、ファミリーレストラン「CASA」に転換するため単身、熊本を本拠地に九州一円を約10か月間飛び回っていたが、西武百貨店の不祥事で和田氏が百貨店に復帰したため、自分も百貨店に戻ることになった。
自分がまだ若いころ、池袋に趣味の街を作ったころにはエルメスは既に池袋店にあった。ジャン・ルイ・デュマ社長は自分と同い年で、アメリカから帰ってから、日本でも西武の独占輸入体制を変えてエルメスジャポンを作りたいと言い出し、かなり対立したが最終的に50:50の出資で合意し、初代社長は元パリ駐在にいた加藤氏にし、自身も役員に名を連ねた。
ルイヴィトンも最初、東京プリンスの地下の西武ピサにあったが、アメリカの銃器メーカーから来た人物を社長にしたいと言われ、もめた結果、日本事務所にいた秦氏を社長にするという話になったが、西武渋谷店1階にショップ出店することになった。ここは修理も請け負える体制にしたため、基幹店として売上も大きかった。だが渋谷店などからは1階にブランドを出すという事が大反対され、社内説得に時間がかかったが、いまや全国で百貨店1階のブランド出店は標準形になってしまったがこれが第一号だった。
無印良品も西武渋谷店への出店が成長のカギとなった。渋谷店の家庭用品部門から大反対されたが、結局これも売り上げが大きく、これによって品質にうるさい百貨店顧客にも支持される無印良品がクラスレスな商品であることが証明された。
ラルフローレンの日本導入も懐かしい。ニューヨークの商社から太いネクタイが大評判になったラルフローレンを紹介され、ライセンス取得し、ナイガイを呼んで、靴下などニット製品のライセンス製造を始めた。これらをまとめてブティックを作った。そのころ松屋の社長だった山中氏から電話があり、これは素晴らしいので松屋の一階でもやりたいと申し入れがあった。しかしダイドー毛織からは、トラディショナル本家のブルックスブラザースより先に西武にラルフロレーンが出店するのはどうだろうかという声も出たので、あとからブルックスブラザースも出店することになった。
堤清二氏は常に初めての取組みにこだわり、高い理想や美意識、デザインなど売上に繋がらないソフトの充実と利益創出の双方を要求したため、高いコストを飲み込むだけの利益がでない事業では苦戦することが多かった。たとえばつかしん開発計画では、落ち葉の上を歩ける落葉街路樹を植えることや、敷地内の川にトンボを飛ばせたいといった話から、この地域が万葉集にどう歌われていたかといった人文的な問いかけが開発コストを膨らませた。
「コミュニティカレッジ」を作った時は現代の寺子屋という位置づけを求められ、先行する朝日カルチャーセンターやNHK文化センターのようにメディアタイアップで講師のギャランティを安く抑えたり、受験ゼミナールの全国統一模擬試験のような利益創出手段が取れなかったので、利益創出にはいつも苦労が伴った。そもそも「コミュニティカレッジ」とはシアトルに出張した折に、街中で発見し、生涯教室はカルチャーセンターではなくコミュニティカレッジという名前だと知り、日本で初めて西武がその名前をつけたものだった。
かつての中元西武では見込み発注商品を積み上げて、期間終了後の売れ残りも多かったが、早割制度を作ったことで、これはかなり解消されたが、「早割でギフトを割り引くことは百貨店の価値を下げる行為だ。」と言われ社内で不評だったが、中元・歳暮のようにお客さまから受注して実際の発送まで20日も30日もかかる商品は事前に数を数を確定して買い取ることで差益を上げることができる。その仕組みを知らずに安売り競争をしたのでは小売業は差益を高めることはできない。
百貨店にとって一番大切なのは、かつて緑屋をクレディセゾンにしたように、また、9期や10期のように、次の時代のビジネスモデルを作る事だと思う。セルフリッジの社長は自営、消化、テンントを分ける理由について、それぞれどの形態が一番利益が出るかによって分けていると言っていた。百貨店はテナントにもっと力を入れるべきでわり、テナントゾーンを得意とするパルコに任せてでも1つ1つのショップをもっと専門度を上げないといけない。情報が利益を出す時代であり、顧客接点となるシューフィッター等の専門職は今後一層大切になると思う。人の使い方が大切であり、本社員のやるべき仕事と任せる仕事の見直しが必要になっていると思う。
G10
元ミレニアムリテイリング副社長、㈱そごう社長、㈱西武百貨店会長
米谷浩
(撮影日:2025/09/25)