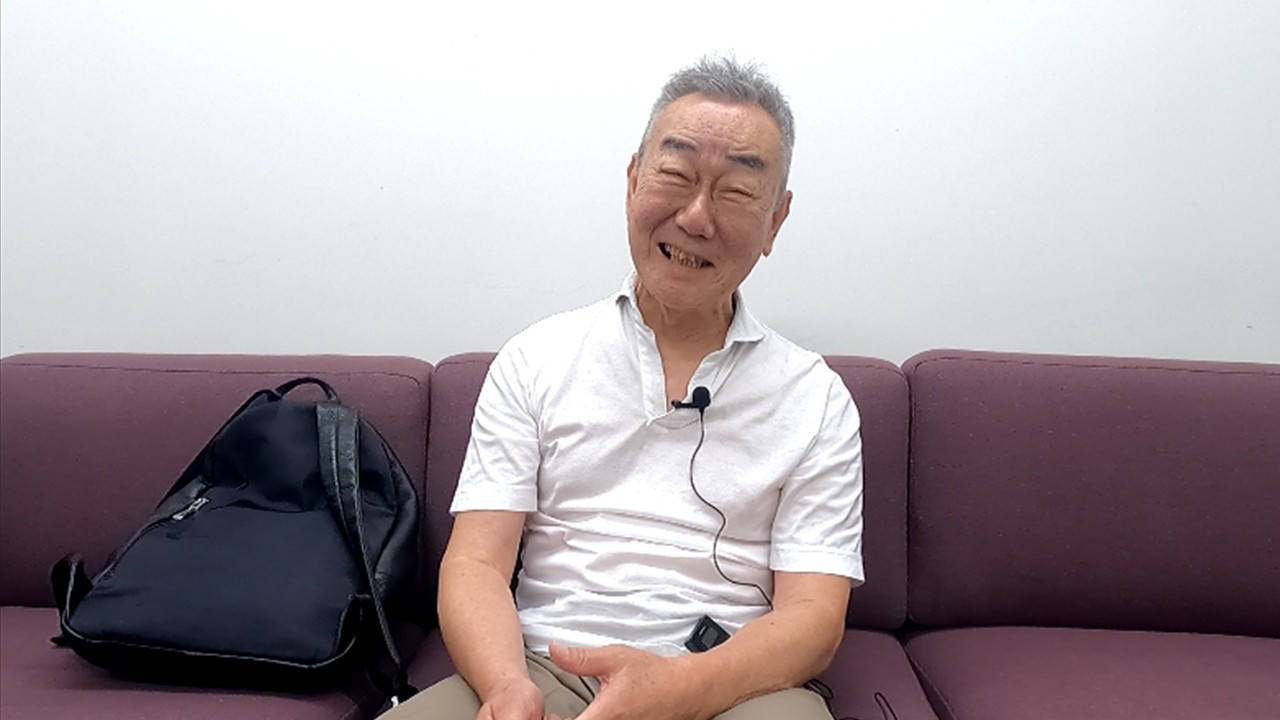東雅春氏は1979年頃入社。西武の文化事業や専門職制度に大きな期待をもって入社したが、実際にはリニューアルを控えた八王子店食品に配属され、組織の論理に苦笑したが、若い自社社員が少ない食品の現場は思いのほか面白く、他部門にない原価管理による自由な値付けができ、勉強になった。2年後にサンシャイン本部の内村氏の営業企画室マーケティング課に異動になり、百貨店の多店舗展開計画に対応したエリアマーケティングや商圏リサーチを西友子会社のスミスと共に行った。上司は後にクレディの社長になる林野氏で、ユニークでジャズに詳しい素晴らしい上司だった。その後新設された商品部AVC部(音映像先端技術部)に異動、これは前職営業企画部長だった山岡氏と共に異動する形になった。当時AVC部ではアップルストア誕生以前に池袋店にパソコンショップ等を展開していたが、同時期に準備が進んでいた六本木WAVEで誰に何を売るかが議論されていた。既に西武セゾングループ内にあったディスクポート西武ではレコード、ヴィデオ等パッケージメディアの仕入販売はできたため、WAVEブランド価値を高めるため音映像の著作権を持ったオリジナル音源や映像の開発が必要だということになった。結論からいうと著作権ビジネスに乗り出すということは流通業としては破天荒なアイデアだが、それを許容・促進する風土が当時は色濃く存在していたのだろう。六本木WAVEは、地上フロアにレコード・CD・ヴィデオ等販売フロアや喫茶、その上に録音やCGのスタジオ、地下に映画館シネヴィヴァンを有する複合ビルとして開業。東氏もここに事務所を移した。当時の構想では、地下でライブ演奏した音源をスタジオで編集し、パッケージメディアを売場で販売するという垂直統合が計画されたが、実際には映画館もスタジオもそれぞれの都合があり、連動計画はできなかった。独自映像・独自音源を作るためアーティストマネジメントに着手し、当時勃興してきたアンビエント音楽やロンドンのiDマガジン編集長をクリエイターに起用したり、環境映像ビデオアートも発売した。著作権のある音・映像アートで世界マーケットを目指そうとしていた。当時WAVEレーベルで発売したアーティストは現在も多く活躍している。また海外のオルタナティブな音楽、E.ノイバウテンやレジデンツ等もライブ開催とメディアを発売した。当時は著作権法務を踏まえた契約書の作り方に詳しい弁護士もまだいない時代で、当時ディスクポート西武にいらした高齢の元キングレコードで独自音源を作られていた堤清二氏の同窓生の大先輩の方から著作権の日本と海外の違いや英文契約書作成など専門的なノウハウを色々教わった。新事業に乗り出す際にこういう先人の知恵は不可欠だと思う。しかしその後の人事異動で得難い専門ノウハウは簡単に捨てられ、誰にも継承できなかったのは残念だった。その後のモノ売りの本業回帰路線で、当時の遺産はニューメディア事業部のチケットセゾン、後のイープラスだけになってしまった。その後横浜山下ふ頭にjazzクラブを開業運営する事業にも携わったが、その後に続くコットンクラブやブルーノートなどの先駆的役割を果たしたのかもしれない。その頃、WAVEの在り方に関心を持った日本最大の不動産オーナーでもある日本生命基礎研究所から各界のビジネスマンと共に呼ばれ、今後の都市活性化の在り方をコンテンツビジネスの視点から提案したが、日債銀か長銀の方からは、「エンタメ・コンテンツビジネスなどビジョンや夢であって産業として成立しない」と否定された。その後バブル崩壊でそれら銀行は破綻し、エンタメ・コンテンツ産業が日本を牽引している事を考えると日本社会の変遷を感じる。
F12
元営業企画室マーケティング課、商品部 音映像先端技術部、六本木WAVE
東雅春
(撮影日:2025/08/27)