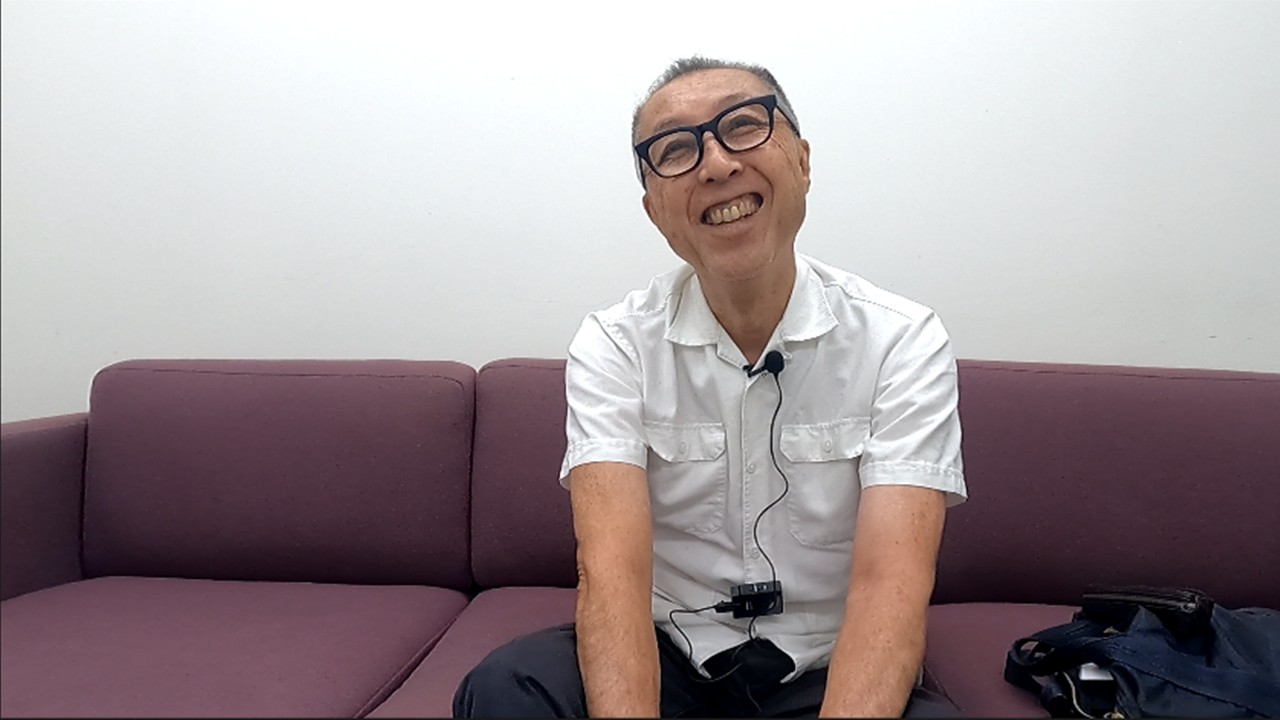①1970年代前半 西武百貨店社員だった頃
1973年武蔵野美術大学卒業後、のほほんとしていて就職浪人になった5月、新聞求人広告を見て西武百貨店家具装飾部に入社。先輩に、後にコムデギャルソンを設計する河崎隆雄氏がいた。最初の仕事は開店直前の渋谷パルコ現場派遣。西武は堤清二氏の構想により流通革命を実験しつつあった。家具装飾部の隣の職場には営業企画部の水野誠一氏がダブルブレストグレーフラノのスーツを着ており、自分もライセンスのサンローランで出勤していた。池袋の駐車場ビルにあったこのオフィスでは堤清二氏とも直にすれ違った。1974年末に在社1年半で退社するが、その退社直前に、図面描くのが初めての新米であったにも拘わらず、熱海駅近くのリゾートマンション熱海サニーハイツのエントランスロビーと併設レストランの設計施工を担当。この空間は50年後の現在も現存する。この西武時代に家具装飾部でスーパーポテトの杉本貴志と出会う。西武の仕事を始めたポテトの営業訪問だったが、渋谷にできたスーパーポテト設計のバー「オレンジ」は、家具装仲間の集まり場であった。西武退職後1年はサーフィンに明け暮れたが、1975年秋、西武池袋店の9期計画が完成。西武美術館と西武ブックセンターが忽然と出現した。美術館横の美術書店アール・ヴィヴァンをスーパーポテトがデザインしていた。ステンレス製グリッド形状で、ソル・レウィットのミニマルアートのようなクールな書店だった。アール・ヴィヴァン社員には評論家の永江朗が、客には大竹伸朗、小沼純一などがいた。スーパーポテトは百貨店自営の西武ブックセンターもデザイン。田中一光指定の紫系に塗り分けられた本棚、コルクタイルの床、こげ茶大理石のイベントコーナーなど、この上なく官能的な本屋だった。後にリブロとなるこの本屋は書店界に風(書店風雲録/田口久美子著)を巻き起こし「今泉棚」など人文系情報発信書店となる。ここに行けば時代の空気が感じられた。併設のカフェ・フィガロもスーパーポテトデザインで、スーパースタジオを思わせるフォルマリスティックでアールデコなカフェだった。ここは蓮實重彦はじめ著名人のサロンとなる。西武は以後、流通産業の変革最前線を疾走する。同じ1975年末、スーパーポテトは、渋谷西武中二階(かつて倉俣史朗によるカプセルショップがあったフロア)に、数年で閉店してしまう超絶なステンレスとガラスのカフェ「パーラーストロベリー」をデザインする。疾走のようなデザインであり、西武の季節だった。
②1976-1985年 スーパーポテト時代と西武の仕事
1976年、こうしたデザインに改めて惹かれスーパーポテトに入社。そのことで以後約20年間、西武の空間デザインに携わることになる。この年、西武の新規出店「ドサ回り」のスタート。物件毎にデザインコミッティが組織され、堤清二直轄の決済システムとなった。綜合デザインディレクターは田中一光。グラフィック系(浅葉克己、日暮真三、青葉益輝、石岡瑛子、小池一子、糸井重里など)、空間系(T-CUP/田中一光+水野俊介、内田繁、杉本貴志の環境チームや乃村工藝など)、建築(菊竹清訓、坂倉建築事務所など)が、セゾングループ企業のクリエイティブを担うことになる。この年の西武大津がスタートだった。パンタグラフ(動物をかたどった棚が斜路に点在するポップな雑貨ショップ)や白昼夢のようなカフェの内装デザインを担当。外構に点在する街路灯はロシア構成主義的な異様なものでこれも担当した。上記のクリエイティブメンバーが新幹線で同行となると、夜は先斗町の宴会に繰り出す昭和な風景が繰り広げられた。1979年船橋西武の改修。西武美術館を担当。モノクロームの空間の中に若林奮のサビ鉄の彫刻を依頼した。同年池袋本店別館にSEIBU SPORTS館がオープン。テニスのビョルン・ボルグ全盛期だった。イリュージョナルなステンレスのサインや連絡通路、そして8階コミュニティカレッジのラウンジロビーを担当(このカルチャーセンターの社員には作家保坂和志がいる)。また地下にはスタジオ200(内田繁デザイン)が作られ、パパタラフマラなど実験的な演劇の発信地となる。1981年、杉本さんとスキー担いで現場監理した旭川amsホール(美術館+ホール)を担当。消費がフル開店したこの頃の「ドサ回り」はコピーライターの西村佳也によれば、富山、大津、渋谷、町田、春日井、静岡、青森、沼津、甲府、前橋、那覇、宇都宮、藤沢、船橋、大宮、旭川、福井、函館などであったという。知名度のない西武は地方ではニシタケデパートと呼ばれた。1983年六本木に音と映像のショップWAVE(内田繁と脇田愛二郎デザイン)がOPEN。地下には斬新な映画の拠点となるシネ・ヴィヴァンがあった(初回の映画はゴダール復活の映画「カルメン」)。以後シネ・ヴィヴァンに入り浸る。同年、有楽町西武開業。百貨店には不向きな小ぶりの店舗で、脱百貨店たることが堤清二会長から発せられる(というか消費の先を見越した物を売らない百貨店とまで考えたらしい。今考えるとEコマースの先駆けか)。よくわからないままにシティスーパーを合言葉のセルフ型デパートとなったが会長には不満が残ったという。1階のカウンターのみのカフェ「スタジオーネ」と売り場空間を担当(編集型セレクトショップであり百貨店に西友の無印良品が入り込んだ)。上階を担当するデザイナー諸氏(近藤康夫、北岡節男、横田良一など)の今でいうPMを担当。同年はさらにOLD NEW 池袋をデザイン。西武百貨店から転じた和田繁明が起案したレストラン西武の新業態。カウンタースタイルのカフェバーで、廃材を寄せ集めた物質感が濃厚な空間。ロゴは田中一光。後に田園調布や京都、神戸六甲(建築安藤忠雄)などに展開する。この多忙な時期に西友のプライベートブランドの案件がもち込まれた。無印良品の最初の独立店舗展開である。青山に見つかった小さな古いビルの改装で、まさか世界のMUJIとなるとは夢にも思わず、短時間でさっと片付ける。しかしノーブランドのノーの感覚は、当時スーパーポテトが入り込んでいたブリコラージュ(寄せ集め)的なデザイン観に合致した。堤清二は無印良品を「ノンフリルマーチャンダイジング=無装飾の商品」として起案したという。無印良品はマーチャンダイジングと思想の間のようなメディアであり、セゾンが産んだ最大の資産といっていい。現在はMUJI FOUNDとして改修されているが、空間の基調は変わらず、入り口の踏み込みの床に、1983年施工の廃物レンガがすり減って残存する。
③1985年以降 独立後の西武とのかかわり
1985年の独立後、西武の大きな案件は渋谷西武SEED館。当時の西武渋谷店長だった水野誠一氏のコンセプトは、多種多様な商品を自在にに編集して寄せ集めるアナーキーさが身上のブリコラージュショップだった。ジェンダーレス、ブランドレス、一見バラバラで当時流行のスキゾ(分裂)的な店舗だった。杉本貴志ディレクションで1.2階を担当、他の階は近藤康夫、松井雅美、横森美奈子など。2階の床にはまな板の樹脂板を使って「アイススケート場」のような雰囲気を期待するも一晩の暖房で膨張し波打つ床に変貌、全ての床を張り替える不幸ではあったが限られた人間の記憶のみに残る空間となった。8階のISSEYの店舗はデヴィッド・チッパーフィールドがデザイン担当。その上のシードホール(映画館)では後の芥川賞作家阿部和重が切符もぎりをしていた。
1987年ホテル西洋銀座開業。コンシェルジュが対応するハイエンドホテルで、ビル内には銀座セゾン劇場が付帯(こけら落としはピーター・ブルックの「カルメンの悲劇」という過激な「セゾン文化」劇場だった)。こうしたセゾンの文化発信事業はセゾン文化事業部が統率。当時の就活で大学生のほとんどは、百貨店なのに文化事業部を志望したという。一時期の文化事業部長は詩人の八木忠栄。この人とは後年花見の会で出会い、寄稿集「花のかい」にエッセイを寄せることになる。
1989年、セゾン美術館(12階からSMA館への西武美術館移転に伴い改名)ミュージアムショップ、地下1,2階の書店リブロ移転計画を担当。売り場が交錯するジャングルのような本屋だった。リブロ担当は中村文孝で、アールヴィヴァン移転の際の什器は90cm立方体フレームを木製で踏襲した。このフォルムはのちのNADiffが展開する東京都現代美術館のミュージアムショップに継続された。分散する書店スタイルでそれらを束ねる広場が設けられ、そのエスカレーター際の吹き抜けには、西武美術館所蔵の作品(ブライアン・クラークのステンドグラス)の設置を提案した。現在もこのステンドグラスは残存する。
1990年 六本木WAVE改装1階メインフロア担当。アルミパイプをパイプオルガンのように波打たせたショップデザインだったが、現在は六本木ヒルズに変貌、WAVEも消失。
1994年 セゾングループの事実上の崩壊後、会長を退任した堤清二に変わり社長となった和田繁明によるリストラ断行の仕事を担当する。西武との関わりの最後の仕事。有楽町西武リニューアル1階、3階、渋谷西武リニューアル2階の改装を担当。百貨店を再措定する大鉈が振り下ろされる。その後西武百貨店はセブンアイホールディングス傘下となるも、田中一光の弟子広村正彰のディレクションにより、店舗空間に松井亮、nendo、永山祐子などを起用し奮闘した。
動画では、他に以下のエピソードが登場している。
1973年ころ西武の建装時代の仲間、黒川、河崎、永井、飯島の4人の名前をまとめたKOKINの会が今も続いており、4人のデザイナーの西武繋がりを知った台湾人ジャーナリストのペギーさんの提案で2021年10月に西武渋谷店美術画廊で4人の作品展を開催し、トランスカルチャーサイトにも掲載されている。当時の西武は何か変化が始まっている予感があった。
自分が西武を辞めてスーパーポテトに入る前に西武美術館、アールヴィヴァン、書店リブロ、カフェフィガロ等上層階がオープンして腰を抜かすほど驚いた。美術館は現代美術でオープンし、アールヴィヴァンはキューブ連続体で彩られ、本屋の棚別ジャンル別の微妙な色分けや赤大理石の特集書籍コーナー、照明アーチや立ち飲みカウンターのあるカフェフィガロも素晴らしかった。これらを手掛けた当時のスーパーポテトは誰もやらないアールデコに現代デザインを掛け合わせた独自スタイルで文化の匂いがした。そして実際多くの文化人の溜り場になっていた。
その後入社試験を受けて1976年にスーパーポテトに入った。当時のスーパーポテトは原宿明治通りで今もビンテージマンションとして人気の高い興和不動産のビラ・ビアンカの一室でやっており、ここは坂倉準三の名作だった。スーパーポテトの杉本貴志氏は独立して最初仕事がなくゴールデン街でたまたま興和不動産社長と知り合い、原宿に最初作ったビラ・ビアンカの近辺にビラ・フレスカを作りさらに作ったビラ・グロリアの地下一階でバーをやらないかと持ち掛けられ、伝説のジャズ喫茶・バー、新宿DUGにいた尾崎浩司氏たちに声をかけ、内装には特徴的な照明入り天井、黒御影石のカウンターや床などで10坪のバーが生まれた。今もバーラジオのカクテルブックで知られるこの店には各界有力者やアーティスト、文化人が集まり、ここからスーパーポテトの歴史は始まった。杉本氏はここで三宅一生氏や田中一光氏や堤清二氏とも知り合った。
その後始まった全国の西武の仕事では常に普通でないものを求められ、売場と売場の合間に曖昧なスパイス売場やスパイス的なコーナーを作る事を求められた。西武渋谷店B館地下一階Be-inでは本屋、レコード屋、喫茶などを一体にした売場を作り現代彫刻のような売場だった。船橋西武の西武美術館にはホール中央の柱を隠すため田中一光氏の提案で現代彫刻家若林奮(あきら)のオブジェを入れる提案があり、具現化され、以降多くの屋外彫刻が軽井沢のセゾン現代美術館にも設置された。
和田繁明氏が西洋フード社長となり、杉本氏が呼ばれ、以降西洋フードの仕事も増えた。スタジオーネやうどんドカフェキララ等ロードサイド店を多数手がけ、カフェバーブームの走りとなるOLD&NEWの1号店が池袋にオープンし人気店となり2022年まで継続し、全国に展開した。ネーミングとロゴは田中一光氏。床壁天井は剥き出しコンクリートで1.9mまでの腰壁には拾ってきた古い鉄板を5cm角に切ったパッチワークを使い、営業的にも大盛況となり、これが契機となり、サントリーの響、赤坂東急ホテルのジパング、果てはスーパーポテト自身で経営する三宿から始まった「春秋」といったバーの仕事が増え、キャナルシティから声がかかり、ついにはシンガポールハイアットに至り、世界中に拡散されていった。スーパーポテトデザインは緊張を解き、食べる事の喜びを空間的に広げるもので飲食との相性が良かった。シンガポールハイアットは1客1万円を超える高級飲食店だが、実は500坪ワンルームの一体空間であり、原点はOLD&NEWであり、さらに杉本氏が好きだった猥雑な新宿ゴールデン街や東南アジアの路地裏飲食だった。現新宿ルミネの旧マイシティにあった飲食街SHUNKANは多数のテナントとバラバラのデザイナーをまとめ上げ隣接店舗の音も筒抜けなレギュレーションを説得してまわり、一体空間を作り上げた。著名なアメリカ人空間デザイナーはここを見て感動し、このフロアを環境と店ごとマンハッタンに持っていきたいと言い出した。ここは古いビルだったので10年持てばよいと言われ、思いきった改装ができた。こうして飲食ゾーンとは環境とそこにいる人間関係と食べ物が一体になって場の空間を作るという実験は次第に定着しセオリーになっていった。
スーパーポテトの作ったものは今もあちこちに残っているが、例えば西武美術館壁面のためにできた旭硝子の壁材ネオパリエは既に全国で使われており、コミカレの雁行する白い壁面もネオパリエだった。池袋駐車場天井にはロシアアバンギャルド風の吊り下げ金具が残っている。コミカレも作った当初は新聞社のカルチャーセンターと同じようなものかと思ったら、現代思想講座まで行う全く異質なものとして今も続いているのは素晴らしい。始めた当初ここまで行くと思わなかったのは青山に1983年に作った無印良品。当時は有楽町オープンや全国のOLD&NEWで多忙な中であり、1週間で提案する超特急仕事だった。外装の古材レンガは水を吸うので寒冷地では水分が凍結膨張して剥離落下の危険性があったが、東京なので大丈夫だという判断が出て進めたが、内心ヒヤヒヤして定期的に見に行っていた。これが評判になり、全国に広がった無印良品だが、飯島氏は大阪アメリカ村まで手掛けた。ミニマリズムに影響されたコンテンポラリーデザインのセオリーは今も健在であり、現在でも銀座店のスキンケア什器に造形家の川俣正や、もの派の菅 木志雄を思わせる造形でありながら、かつシステマチックなものが登場したりしている。これは今も小池一子氏、原 研哉氏などがボードメンバーに参加していて軸がブレていないからだろう。
2027年2月には、昔スーパーポテトがロビーラウンジカフェのデザインを手掛けた目黒区美術館でスーパーポテトの展覧会が開催される予定になっている。