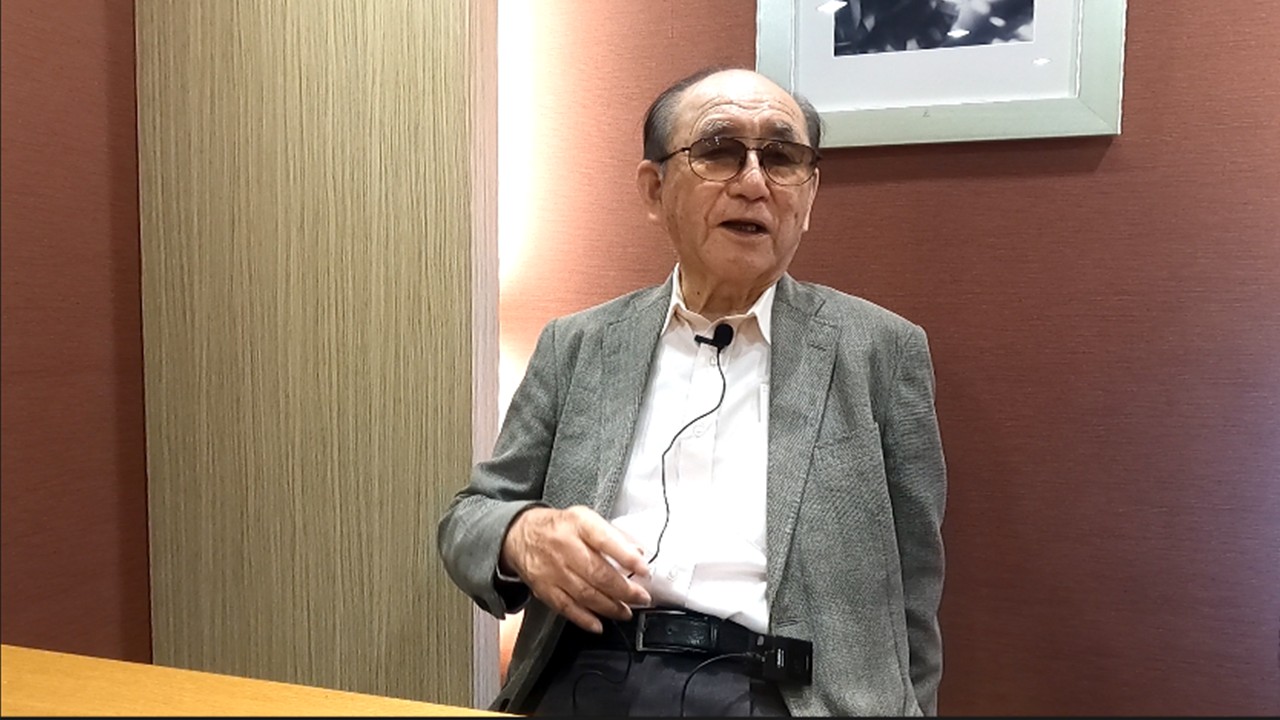今井亮氏は1959年(S34)年入社の大卒4期生。上には1期竹内氏、2期和田氏、3期米谷氏がいた。不景気で西武には大卒で730人応募があったが入社は19人だけだった。自分は三越でアルバイト経験があり、当時花形の2階ネクタイ売場に配属された。全員女性で1人だけの男性社員だった。歌声喫茶の時代で、販売長指示ですぐ売場コーラスグループの指揮をさせられた。後にワイシャツ売場に行き係長に。仕入れは先輩の1人だった。1963年に最若年の商品部バイヤーに。だが販売部と販売部の折り合いが悪く、この年には池袋紳士池袋店火災もあり、商品部は一旦消滅。谷島氏の下の営業企画に。そのころパリの邦子部長がスタッフを求めていて、子供が生まれたばかりで心配だったがパリ駐在へ。帰ってきて1966年から再度、趣味雑貨出身で衣料未経験だった和田紳士服部長の下で注文服を担当。木勢氏、横堀氏もいた。ここではダンディサロンという売場内にパリ帰りの五十嵐五十九氏がコーナーを持ち、堤氏が三島由紀夫氏の盾の会の制服を受注し、体にフィットした有名な制服を作った。自分も仮縫いに立ち会った。パリで邦子部長に連れられサンローランやルイフェローやテッド・ラピドスに一緒に行ったがフランスでは型紙ではなくトワール(型布)をトルソーに載せて裁断する立体裁断・立体縫製中心だったので顧客の体にフィットしたが、当時の日本は型紙で作る方式の英国屋や一番館など、ややルーズなフィット感の英国式だった。当時は三越、高島屋に負けない顧客開拓を目指し、米谷氏の兄上の繋がりでダークダックス、そこからボニー・ジャックスのステージ衣装も西武の注文服で承った。次に呉服部長を拝命。初めての世界だったが、紳士ネクタイの産地でもあった西陣での繋がりが活きて3年間勤め、婦人服部長になった。当時店長は財界から来た三好氏、豊島氏が商品部長。山崎前店長が関西に転じたため、販売部長になったが、西友上場に向け、三好氏と豊島氏の二人が西友に移る事になり、当時三越から来た坂倉社長は、三越でも昔進駐軍のパージで上層部がいなくなり、若手の自分が仕切っていた位だから、40歳と若い今井氏でも店長は勤まると堤氏に掛け合い、自分が店長になった。そして9期計画が始まった。1973年~74年のオイルショックで堺屋太一の「油断」がベストセラーになった頃、池袋店は12階まで増床し、池袋駅には有楽町線南側コンコースもできた。堤氏は美術館や公園のある街づくりを提唱し、売上日本一を目標に掲げた。当時の環境計画は最旬だった鈴屋の木の環境が予定されていたが、内装業者がつぶれてしまい、木の環境は今がピークなのではないかと考え直した。そこでメタルやガラスを多用した次世代環境をテーマに掲げた。堤氏は美術館を現代美術中心とし、全て最新を目指した。そのころ堤氏と同年で親しかったサンリオ創業者の辻信太郎氏の勧めでアメリカ、カンサスシティのホールマーク社を訪問し、ホールマークの隣にあったホールズという専門店集積型百貨店を訪問し、西武池袋の改装計画や売上日本一を目指すことを説明したが、先方から量の計画は分かったが、質の計画は何かと問われ、答えに窮した。ホールズはライフスタイル別に1階はカジュアルライフスタイル、2階はエレガンス、3階はシック&フォーマルでそれぞれ、靴もバッグも服も別々であると説明し紹介された。当時の日本はアイテム集積ばかりでライフスタイル別マーチャンダイジングは初耳だった。ショックを受けて、その後のニューヨーク行を中止し、急遽帰国。9期コンセプトは堤氏の街づくりとともにライフスタイル別マーチャンダイジングとした。これを象徴するのが日常の暮らしをお洒落にするオーマイダイニング。普及し始めた様式トイレのグッズも揃えた。朝食をお洒落にするザ・ブレックファストも作った。関連商品としてチーズやヨーグルトやパンも充実させた。保坂氏のアイディアで日常普段着のお洒落を目指す衣料品のエブリデイも開発した。他にもお洒落なシャツの売場、さらにロアジール館も誕生。当時週休2日制が取りざたされ、季刊ロアジールが発行され、「仕事の合間の休暇」ではない余暇生活の充実が叫ばれた社会に応えた。それに合わせショップマスター制度も作った。マイスターなど職人を大切にするヨーロッパ社会に範を求め、係長、課長、部長という管理体系に拘らず年齢や学歴や性別を問わないそれぞれの道の専門家に平等にショップを任せる専門性ある売場の集合体を未来の姿として目指した。これは何でもある従来型百貨店ではない専門大店構想だった。政治の世界は今も右から左までなんでもある自民党がやっているが、それではないだろう。6年間の商品部長でルイフェローもサンローランもテッドもやったが、エルメスは西武が総代理店だったのをデュマ社長がエルメス社と西武の50:50出資のエルメスジャポンにしたいと言い出し、交渉した。結果的にそうなり、役員会はパリと日本で毎年1回ずつ開催した。後にはエルメスジャポンの社長もやった。当時は商品部が海外駐在を統括し、パリ、ロンドン、ミラノ、北京などに駐在所があった。ファッション以外にヴァン・クリーフ・アンド・アーペルなど宝飾ブランドもあった。ミラノではミッソーニやフェレやベネトンもやった。南仏のソレイアードも邦子さんが見つけてきたし英国リバティもあった。不調になったリバティ社からは西武で買収できないかという相談もあった。ロンドンは小澤所長が長くやってくれた。英国コンラン卿とは何度も交渉し、日本でコンランの商標が使えずハビタジャパンとして池袋店向かいの旧緑屋のビルをハビタ館としてスタートしたが、元々コンランの店はパリもロンドンも古いビルのリフォームでできていた。これも新しい生活様式を求めるライフスタイル型マーチャンダイジングだった。ずっと後になって新宿東京ガスのビルにコンランショップもできた。堤清二氏とは何度も衝突したが、彼はいつも現状否定で新しいものを求めていたが、完成すると飽きてしまう傾向があった。いつも次の時代、次の世の中がどうなるかを知りたがっていた。堤氏は時流を読めと言っていたが、それは政治も経済も文化も合わせた社会の変化に対しどんな商品を提案するのかを問うものであり、それが西武の商品部の仕事であり、商品部は仕入れ部ではなかった。日々の仕入れは売場に権限移譲されていた。商品部にとっては、半期に一度社内向けに開催される開発商品展示会が主戦場であり、苦しみながら新しい提案を半期ごとに作っていた。もう一つ堤氏は「価値は分量なり」と言っていた。つまり、小さな規模の価値あるものを見つけて大きくすることが大切であり、大きくなると価値はなくなり、次第に普遍なものになっていく。ファッションだったものがスタイルになっていく。ジーンズ等が好例だろう。自分はこういった堤氏の言葉を今も考えていて母校の校友会副会長でそのことを言うと煙たがられている。最近読んだ本だがテクノ封建制というのがあって、農民は昔貴族に搾取され、次に武士に搾取され、それが大商人に代わり、明治維新で官僚や軍人に代わった。戦後は資本家に代わったが、いつしかどの国も議会など省略され専制君主が出てきている。そして今や戦争さえもGAFAなしには行えない時代であり、これが封建領主化していて、中間層は没落し百貨店顧客は減っている。ある程度は国がこれらを規制しないと19世紀社会に逆戻りだろう。テクノロジーは誰もコントロールしない。また線状降水帯や海面上昇など温暖化では低地の国は消滅の危機になっている。台風は日本近海で発生するようになった。テスクリアル時代のテックライトは自分たちの子孫以外の人々の消滅は不可避だと割り切っている。堤さんが生きていたら何というか。スマホ漬けの若者を見て何というか。ライフスタイル別MDを分かってくれた堤さんはどう考えるか。池袋の地下2階を新設したときは台湾の百貨店の5階や6階にあった裸火が盛大に上がるイートインとテイクアウトの兼用料理店を参考にしたもの。これは台湾の百貨店の経営者にアイディアを出してもらった。日本では裸火は不可で電気式にしたが、インド料理はアジャンタなど世界各国の本格的料理を提供した。
G3
元西武百貨店常務取締役 (株)リプロジェクト・パートナーズ監査役
今井亮
(撮影日:2025/09/10)