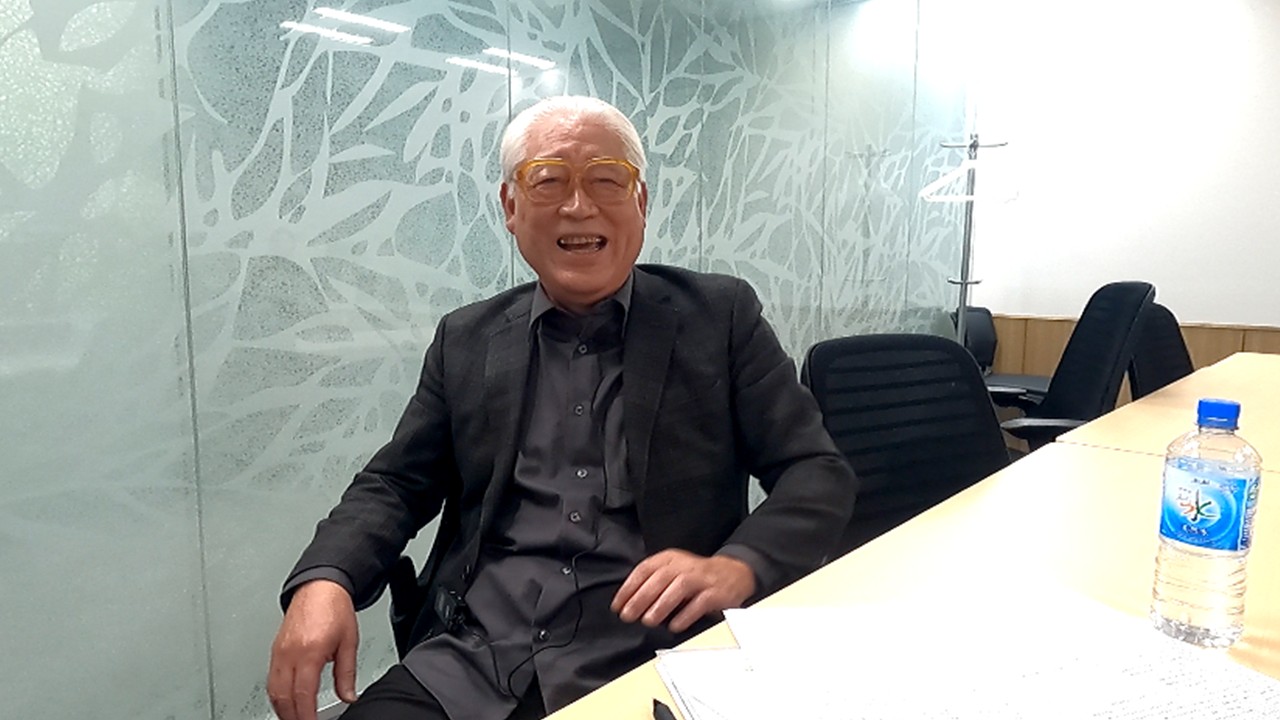荒井紀雄氏は1971年に約230名の同期と共に西武百貨店に入社し、船橋店婦人雑貨課に配属された。この年は「西武流通グループ」が発足し、世界最大の小売業だったアメリカのシアーズローバック社と提携した年だった。シアーズカタログは電話帳のようなサイズで全米の田舎まですべての家庭に置かれ、あらゆる品物をカタログ通販していた。1963年に西友ストアが設立され、西武受験の前に保証人をお願いした、当時西武百貨店から西友に移られ商品部畜産部長をされていた方から、「これからはストア(GMS)の時代だから西友に来たらどうだ?」と、勧められたが私は未だGMSに馴染みがなくお断りした。この時、この方から「百貨店に入ったら美術や芸術の知識を身につけるようにしなさい」とアドヴァイスされ、後々ようやくその意味が分かった。
2年後に船橋店販売促進課に異動、赴任した初日に、チラシの通販コラムの商品コピーをその場で考えるように指示され、大変な部署に来てしまったと困った記憶がある。船橋店時代の一番の思い出は、1978年オープンの大増床計画で、「ストップ・ザ・日本橋」をテーマに、西武の多店舗展開モデルの本格的百貨店の1号店づくりに参画できたこと。当時はほぼ年中無休で月の残業時間が150~200時間で毎月がボーナス並みの給与であった。この時の上司課長が福田昭彦氏で、その後「㈱セゾンダイレクト」から現在の「㈱くらしのセゾン」まで、引き続いてお世話になっている。
1984年に渋谷店販売促進担当に異動、翌年85年に営業企画部部長、同年に「西武セゾングループ」が発足した。渋谷店は水野店長をリーダーに、どこにもない当別な店「オンリーワンストア」を目指して活動した。1985年「ジャパンクリエイティブ展」、1986年「渋谷SEED」・1987年「LOFT」オープンと、立て続けにビッグプロジェクトに参画した。「ジャパンクリエイティブ展」は、田中一光氏の「JC」のロゴの下、100有余の「作り手・助け手・使い手」各界クリーエーターの参加を得て、日本のモノとコトを現在感覚で見立てた全館催事として開催、内外から多くの称賛を受けた。これは無印のようなベーシック志向ではない百貨店らしい遊びと付加価値性のある商品群だった。その後全社展開の自主MDになり、JCの名称と思想・活動は現在も引き継がれている。
「渋谷SEED」は、田中一光氏が指名した井上嗣也氏のロゴとグレーのカラーリングに「なんだか不思議な種である」をキャッチコピーに、自主開発MDで構成したアパレル中心の独立館であった。現在は無印館になっている。ここの10階には自主企画で展開する多目的ホール「SEED HALL」を設け、林牧人支配人の下、映画興行館も兼ね、前衛映画から現代美術まで時代の象徴となるような企画運営し、今も語り草になっている。また山本寛斎氏のカラーリングによるレーシングチーム「SEED RACING」で鈴鹿8時間耐久レースに参戦、6位入賞も果たした。その後SEEDは閉館したが、店の前の「NANAKO」(ハチ公の妹)の名前をつけた猫の石彫は今でも健在である。
「SEED」の館名とロゴの堤会長プレゼンの際、水野店長に同行して立ち会った時はちょうど前年に有楽町西武がオープンした時期であり、会長から「渋谷マリオンが良いね!」との提案を受けたが、水野店長はマリオンとは業態が異なるとして、何度かの押し問答の末、頑なに拒否した。水野氏は帰店後「マリオンという名前がついたら俺は西武をやめる!」というほどネーミングに真剣だった。その結果「SEED」で無事に押し切ったのも貴重な思い出だという。この会長プレゼンの時、水野店長到着が30分ほど遅れ、荒井氏は会長室で会長と二人だけになった。この時会長は荒井氏の目の前に座って、「君はどこにいるんだね?何をやっているんだね?」~「西武渋谷店で営業企画部を担当しております」~「そう、君ねえ、百貨店のバカになるなよ!」~「・・・」~「百貨店の役員どもはみんなバカばっかりだ!」「いいか、そんな奴らと同じ百貨店のバカになるなよ!」~「・・・はっ、はい・・・」~早く水野さん来てよ!と思ったという。これが会長からマンツーマンで指導された唯一の機会だったという。
「LOFT」では、店舗環境とプロモーションを担当、LOFTのストアコンセプトは「LUDENS館」(ホモ・ルーデンスに由来する“遊び心”)、名称は社内外から募集して選定、田中一光氏・小池一子氏・杉本貴史氏の開発コミッティのアドヴァイスを受けながら、店舗外装の色は田中さんから提案された「深川鼠」色とし、店舗入口の角に「道祖神」・「間坂」沿いの行灯・「間坂の拓本石柱」、脇田愛二郎さん制作の「石灯籠などの石彫モニュメント」を配し、公園通りへの抜け道つくり=「間坂」通りを石畳貼りに変えて名所化した。「間坂」の名称は、渋谷図書館の文献に、昔の渋谷村に「暗闇坂(くらやみざか)」と「間坂(あいだざか)」があったことから、公募形式で「間坂」に決めた~“まさか!ここから公園通りに行けるなんて!まさか!こんな通りにロフトがあるなんて!”と意外性を込めて名付けた。今では地図にも載っている名所通りとなった。ロフトの黄色とロゴは田中一光氏で制服も黄色でショッピングバッグも黄色で、ロフトから駅までの人の流れが黄色く染まりイエローリバーと呼ばれる大盛況となり、この渋谷のイエローリバーが日本各地に広がっていった。
渋谷西武では、1984年の「フランス展」をスタートに、「イタリア展」「スペイン展」「中国展」「香港展」「バリ展」「インド展」「英国展」、更に日本初「キューバ展」と、5年間で9本の海外催事を開催、本部連動とはいえ現場を運営する店側としては目が回る大変さであった。西武の海外催事はその多くを雑誌ブルータスとのタイアップで開催し、ニューヨーク展ではブレイクダンスを日本に紹介し、スペイン店では後のジュリアナの扇子踊りを日本に初めて紹介するなど先進的な海外文化の日本紹介の場であった。日本に紹介しその後定着した商品も数多く、スペイン展では宝飾のヤーネスやシビラなどスペインブランドやデザイナーも日本上陸した。
渋谷にいた5年間は30代の働き盛りでもあり、荒井氏にとっては、しんどくとも生涯で一番楽しく働いた時代であり、同時期に同じ釜の飯を食った「元シブ西組」30余名の仲間との付き合いは今でも続いているという。その後、1998年㈱セゾンダイレクトマーケティング、2006年㈱ロフトを経て、元の上司の福田氏に呼ばれ、2020年から㈱くらしのセゾンで勤務中であり福田氏とは半世紀にわたる上司と部下の関係だという。荒井氏は衣食住のあとの遊休知美体事業を追求したセゾングループの活動のその後のあるべき姿を下の図で考えているという。